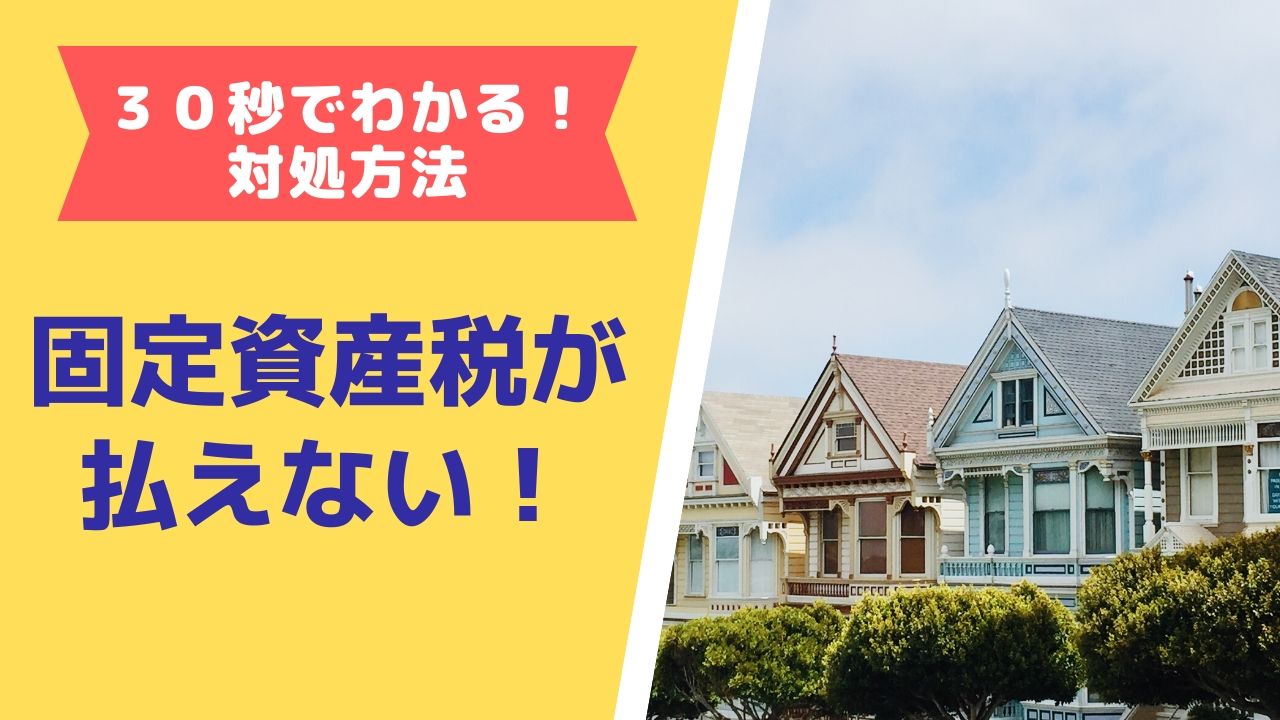
固定資産税は、所有する土地や家屋に対してかかる税金で、毎年1月1日を基準日としてその所有者に課税される地方税です。
固定資産税の支払いはほとんどの市町村で年間4期に分けられており、具体的な期日は市町村によって異なります。
納め方は、1期ごとに納めても良いですし、1年分をまとめて支払っても良いところがほとんどです。
では、万が一その固定資産税を延滞するとどうなるのか、具体的に見ていきましょう。
いますぐできる対処方法として、一時的にカードローンで建て替えるのもアリですね。
プロミスなら「はじめての人は30日間利息0円」で「WEBからであれば最短3分融資も可能(※1)」です。
レイクはテレビCMでもおなじみの人も多くて安心
アコムなら「最大30日間金利0円」、最短30分で借りられる。
※1)お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※無理な借入を推奨するわけではありません。ご利用する場合は計画的にお願いします。
固定資産税を滞納するデメリット
督促される
もともとの納付期限を過ぎると20日ほどで督促状が郵送されます。
督促状は納付書と兼用になっていることが多く、通常はそれをもって銀行等へ行けばすぐに納付できるようになっています。
市町村にもよりますが、納付しない場合は期間をおいて数回この督促状がとどきますが、どうせ数回来るならと放っておくのはNGです。
法律上、督促状発送後10日が経過すると、いつ差押えを受けてもおかしくないということになります。
分納や猶予を希望する場合は出来るだけ早い段階で相談にいきましょう。
延滞金がかかる
滞納が発生した翌日から延滞金がかかってきます。
利率は市町村によって多少異なる場合がありますが、納期限後1か月までが2.7%程度、納期限後1か月以降9.0%ほどの利率です。
信用を失う
滞納を続けていると、強制執行(差押え)に向けて財産の調査がスタートします。
銀行などの預金の調査や、解約返戻金のある保険の有無を保険会社等に調査されることはもちろん、事業主の場合は、取引先にまで調査が行われることがあります。
万が一取引先に調査が行けば、信用を失い、事業取引自体なくなってしまう可能性もあります。
差押えされる
督促を無視し続けていると、次は催告状が届きます。
強制執行に入る旨が記載され、ほとんどの場合は最終納期限が記載されています。
その日までに納付をしなかった場合、財産や不動産など金銭に代わるものの差押えが執行されます。
口座に残高がほとんどない場合も、調査の段階で給料日や年金支給日を把握していることが多いため入金後すぐに差押えられる可能性があります。
競売にかけられる
差押さえた財産が不動産の場合「公売」で売りに出されます。
市役所等が税金の滞納処分のために売却を行うことを「公売」といい、この場合は裁判所が間に入ることも不要とされています。
差押さえられたものが預金等の財産だった場合、定められた割合を固定資産税を納めるために引き落とし、納税を済ませて差押えの解除となります。
納付金額が滞納分に満たない場合は、このような預金の差押えと納税を繰り返し、満額納付になるまで続けられることが多いようです。
自己破産でも免除されない
自己破産をしてすべての借金等を帳消しにする方法もありますが、たとえ自己破産をしても固定資産税は借金ではないため免除となりません。
自己破産後、少しずつでも返済する義務が残りますので十分に理解しておきましょう。
固定資産税の支払いを待ってもらうことは可能なのか?
固定資産税をどうしても納めることが出来ない場合、一定の条件を満たせば徴収の猶予を認めてもらえることがあります。
この場合、期間中は全く払わないということではなく、分納で納付をしていくことになります。
条件としては、滞納の原因が、災害・盗難・病気・ケガ・事業の廃止/休止・事業での多大な損害などに当てはまる必要があります。
徴収の猶予を利用した場合、延滞税が減額や免除となり、新たな差押えが出来なくなります。
現在すでに差押えをされている場合でも条件を満たせば差押えが解除が可能になります。
手続きは簡単ではありませんが、メリットも多いので申請できる方はしてみると良いでしょう。
滞納している固定資産税の免除は可能なのか?
滞納処分の停止
本当に支払い能力がない場合、要件を満たし役所の承諾を得られれば滞納処分の停止という制度を利用することが出来ます。
利用条件は以下の通りです。
1)滞納処分を執行できる財産がないとき
2)生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
3)滞納者の住所と財産がともに不明であるとき
この要件を満たすすべての人が利用できるわけではなく、役所の承諾を得る必要があります。
この制度はあくまで納める側に否があることを前提に支払い義務を免除してもらうものであり、実際の認定はかなり難しいものとなっています。
この申請は権利ではなく、あくまで「お願い」であることを忘れずに相談してみましょう。
固定資産税の未納分の分割払いは可能なのか?
固定資産税はもともと1年分を4期に分けて分納するものとなっていますが、それをさらに分納することや、未納分の分納も相談次第で可能です。
分納の方法は大きく分けて3つあります。
それぞれについて順にご紹介します。
通常の分納
窓口や電話での相談内容に応じて分納する方法です。
滞納理由・預貯金や不動産等の詳細・分納の回数や金額を大まかにヒアリングされ、役所側と相談の上、分納を決めていきます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
・手続きが簡単 ・出来る範囲での支払いが出来る |
・延滞税がかかる ・申請時にまとまった金額を納税に当てる必要がある |
徴収の猶予
病気等で働けない方やや事業の不振で延滞をしている方は、状況によっては「徴収の猶予」という制度を利用できる可能性があります。
■徴収の猶予を利用するための要件
1)災害や盗難にあった
2)本人や家族の病気・ケガ
3)事業の廃止・休止
4)事業で大きな損失を被った
5)上記に似た事象がおこった
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
・延滞税が免除もしくは減額となる ・差押えができなくなる |
・手続きが面倒 ・申請が通りにくい |
換価の猶予
換価の猶予とは、すでに差押さえられたものの売却に対して猶予をもらう制度です。
徴収の猶予よりも厳しいとされており、実際に制度を利用できる人は限られています。
■換価の猶予を利用するための条件
1)すでに財産を差押さえられている
2)財産の売却により、生活の困窮、事業の継続が難しい状況が予想される
3)換価の猶予を受ける税金の他に滞納をしていない
4)納税をするという誠実な意思がある
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
・延滞税が50%免除となる ・差押えとなっても売却を先延ばしに出来る |
・手続きが面倒 ・申請がかなり通りにくい |
滞納している固定資産税に利息はつくのか?つくならどれぐらい?
固定資産税を滞納するとその翌日から延滞金がかかってきます。
各市町村によって若干異なる場合もありますが、おおまかな例をご紹介します。
特例基準割合
これが延滞金の基準となる利率です。
期間によって利率が異なるので注意が必要です。
| 平成12年1月1日~平成13年12月31日まで | 4.5% |
|---|---|
| 平成14年1月1日~平成18年12月31日まで | 4.1% |
| 平成19年1月1日~平成19年12月31日まで | 4.4% |
| 平成20年1月1日~平成20年12月31日まで | 4.7% |
| 平成21年1月1日~平成21年12月31日まで | 4.5% |
| 平成22年1月1日~平成25年12月31日まで | 4.3% |
| 平成26年1月1日~平成26年12月31日まで | 1.9% |
| 平成27年1月1日~平成28年12月31日まで | 1.8% |
| 平成29年1月1日~平成29年12月31日まで | 1.7% |
具体的な利率
■平成25年12月31日まで
1)納付期限から一か月を経過するまで・・・特例基準割合
2)納付期限から1か月以降・・・年14.6%
■平成26年1月1日以降
1)納付期限から一か月を経過するまで・・・特例基準割合+1%
2)納付期限から1か月以降・・・特例基準割合+7.3%
平成26年度から大幅に利率の見直しがされました。
延滞金の計算をする場合、この期間で大きく違ってくることを理解しておきましょう。
また、26年以降は利率が下がっていますが決して低い金利とは言えないことを理解し、出来るだけ延滞金をかけることなく納付できるように努めましょう。
固定資産税が払えないときの良い対処方法
素早い相談
固定資産税が払えないとわかった時点や、延滞をしているとわかった時点ですぐに市町村の役場に相談しましょう。
すぐに相談することで、納める意思があることを示すことになり、また救済措置の選択肢も広がります。
分納を検討する
上記の相談にも共通しますが、役場との交渉で分納が可能な場合は、月々支払い可能な金額で分納を交渉しましょう。
まとまった金額では納付が難しくても、相談によって無理のない支払いをさせてもらうことが可能です。
この場合、徴収の猶予を使えば延滞金を抑えることもできるのでそういったことも含めて相談してみましょう。
家族や親せきに相談する
分割を利用しても支払えない場合や、分割が不可能な場合、延滞を続けていればいずれは差押えされることになります。
そうならないためにも、一度身内に相談し、納税資金を貸してもらえないか交渉してみましょう。
この場合、必ず借用書を残し、返済を必ずすることを約束することが大切です。
固定資産税が払えないときのダメな対処方法
放置する
もっともダメな対処法です。
督促状が届いて滞納に気が付くという方もおられると思いますが、その時点ですぐに納付すれば大きな問題はありません。
もし支払う余裕がないのであれば、役所へ相談に行きましょう。
納付も相談もせずに放置していると、意図的な滞納、悪質な滞納と判断され、せっかくの分納の可能性まで失くしてしまうことにもなります。
最悪の場合、差押えによって家や財産を失うことにもなりかねません。
放置することなく、必ず何かしらの対処をしましょう。
安易に自己破産する
他にも借金などがあり、それらも含めて支払いが出来ない場合は自己破産も選択肢の一つですが、固定資産税の滞納から逃れるためだけに自己破産をすることは止めましょう。
というのも、自己破産をするとすべての債務が帳消しとなりますが、固定資産税は債務ではなく税金であり、自己破産をしたからといって免除されることはないためです。
闇金など違法な貸金業者から借りる
しっかりと返済計画を立てたうえで、銀行や消費者金融から一時的に借りることは悪くないと思いますが、返済予定も立てられないまま闇金などからお金を借りてしまうことは絶対にNGです。
さらに借金を増やすことになり、今回はよくても次回の固定資産税を支払うことが実質不可能となるでしょう。
固定資産税が払えなくなったらどこに相談すればいいのか?
市町村の納税課・資産税課など
固定資産税の納税に不安があるときや、実際に滞納をしてしまった場合ですぐに支払いができないときには、出来るだけ早くその資産のある市町村の役場に相談してみましょう。
忙しいからと先延ばしにするのではなく、電話一本入れるだけでも印象が違います。
その後の分納交渉などをスムーズに進めるためにも誠実な態度で相談をしてみましょう。
お金が足りない場合は一時的にカードローンで対処するのもアリ
※1)お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※2)申込の曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱となる場合があります。
この調査内容の総括
家や土地に課せられる固定資産税を滞納した場合の対処法についてご紹介しました。
預金などが無くても不動産を持っていることでかかる税金なのでどうしても支払いが出来ないということも起こり得る税金ですが、それをそのまま放置することは絶対にしてはいけません。
安易な気持ちで滞納を続け、気が付けば家を失ったということもあり得ます。
税金なので簡単に免除はされませんが、事情をしっかり説明し、納付したい意思はあることが伝われば、分納や猶予といった制度を利用することも可能です。
悪質だと判断された場合にはこういった制度が使えなくなることも多々あるので、あくまでも低姿勢で相談に臨みましょう。
また、そうならないためにも、日ごろから少しずつ計画を立てて納税資金を積み立てておく、期限に余裕があってもまとまったお金が入った時点ですぐに納める、というように生活に応じた対応をしておくことが大切です。





